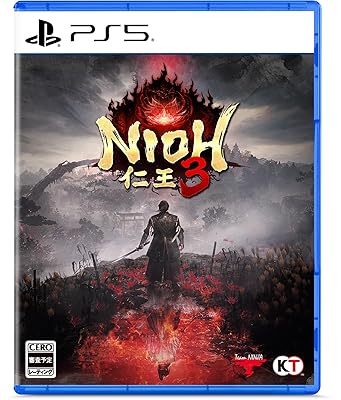Team Ninjaの最新作「仁王3」が2026年2月6日にPS5とPCで発売。徳川竹千代を主人公に、時を越える物語が展開します。「セミオープンワールド」による探索の自由度と緊張感の両立、そして「サムライ」と「ニンジャ」という二つの戦闘スタイルの特徴とは?プロデューサー柴田剛平氏へのインタビューをもとに、シリーズの進化点を解説。
2025年6月の配信イベント「State of Play」で初公開され、9月の東京ゲームショウでは試遊も実施された、Team Ninja開発のダーク戦国アクションRPG最新作「仁王3」。世界中のファンの期待を集める本作の発売日は2026年2月6日、プラットフォームはPlayStation 5とPC(Steam版はダウンロード専売)です。
本作はシリーズの代名詞である「死闘感」を継承しつつ、「セミオープンワールド」と「タイムトラベル」の2大要素でシリーズ最大の進化を遂げています。Team NINJAブランドプロデューサー柴田剛平氏へのインタビューをもとに、作品の全体像と、その革新に込められた開発の意図を詳細に明らかにします。
時を越える壮大な物語
「仁王3」の物語の根幹は、徳川家康の孫である「徳川竹千代」の運命から始まります。元和8年(1622年)の江戸時代、次期将軍の座を巡り、闇の力に魅入られた弟・国松が妖怪の大群を率いて江戸城を襲撃。平和な日常は一瞬にして地獄へと変貌します。この窮地に陥った竹千代は、守護霊「草薙」の力によって時を越える能力に目覚め、自らの運命と歴史の災禍に立ち向かう壮大な旅に出るのです。
物語は、泰平の世から始まるからこそ、戦乱に突き落とされる主人公の境遇が際立ちます。旅の途中では、武田家と徳川家が激戦を繰り広げた戦国時代、そして源頼朝率いる鎌倉武士たちが跋扈する平安時代など、複数の時代を駆け巡ります。古代邪馬台国の女王・卑弥呼といった歴史上の人物とも出会うことになります。
「時を旅する」というアイデアは、開発陣が本作で挑戦したかった「オープンフィールド」のデザイン上の課題を解決するための手段でもあった点が興味深いと、柴田氏は語ります。広大なマップの異なるエリアをプレイヤーが容易に認識できるように、視覚的に劇的な変化を与える必要があり、その最も効果的な方法として「完全に異なる時間軸を見せること」を結論付けました。この開発の透明性を維持しつつも、柴田氏は「タイムトラベルは、主人公・竹千代の葛藤と成長、そして壮大なスケール感を示す上で不可欠な物語の柱である」ことを強調しています。プレイヤーはキャラメイクによって自分だけの竹千代を生み出し、この壮大な歴史の渦に身を投じることができます。
高密度なセミオープンワールドの設計思想
本作が目指したのは、単に広大な空間を移動させる「完全なオープンワールド」ではありません。シリーズならではの緊張感と密度を維持しつつ、探索の自由度を拡張する「セミオープンワールド」構造を採用しています。
シリーズ初のオープンフィールド型のマップへの移行は、開発チームにとって大きな挑戦でした。「探索の自由度を確保しつつ、プレイした瞬間に『仁王』だと感じられる緊張感を維持することに注力しました」と柴田氏は強調します。
開発過程では、アクション性を意識しすぎるあまり、敵を配置しすぎた結果、戦闘が単調な作業になりかねないという課題に直面しました。この課題を克服するため、開発チームはフィールドの「密度に緩急をつける」設計を採用しました。プレイヤーに、敵が多く集まるエリア、少数だが非常に強い敵がいるエリア、あるいは通過自体が困難なエリアなど、戦略的に進路を選択できる多様な進行方法があることを認識してもらうことに焦点を当てたのです。この試行錯誤の結果、広大な探索の自由度と、常に死と隣り合わせのシリーズならではの緊張感が共存する、独特のフィールド体験が実現されました。
二つの戦闘スタイルが描く新たな戦闘哲学
本作における最も大きな変革の一つが、「サムライ」と「ニンジャ」という二つの戦闘スタイルの導入です。この設計思想には、開発チームの日本の武に対する深い解釈と、特定の戦闘技術への深遠な専門性を追求するこだわりが色濃く反映されています。
サムライは「構え」と「流」を駆使する重厚なスタイル、ニンジャは構えを廃し忍術や空中アクションで翻弄する立体的なスタイルと、それぞれに明確な特徴があります。重要なのは、武器種が各スタイルに排他的に固定されている点です。例えば、鎖鎌やトンファーはニンジャにのみ、槍はサムライにのみ使用が限定されています。
柴田氏はこの分離について、プレイヤーの自由度を「制限」するためではなく、「各スタイルの専門性を極限まで高め、戦術的役割を明確にするため」の意図的なデザインであることを強く説明しています。
「(両スタイルで)武器が使えるようにすると、二つのスタイル間の明確な要素が少し曖昧になってしまいます。私達は二つのスタイルを明確かつ深遠に保つことが重要だと考えました。」
刀のように両スタイルで使える共通武器もありますが、サムライが頭上に掲げるのに対し、ニンジャは背後に構えるなど、モーションや使い方が根本的に異なります。これは、単なる制限ではなく、各スタイルを極めるためのテーマ的整合性と深い技術的合理性に基づいた、開発チームの哲学が反映された結果です。この意図的な分離により、ベテランプレイヤーであっても、それぞれのスタイルで新たな学びが必要となる深みが生まれています。
遊びやすさの追求とQoL改善
シリーズの代名詞である高難易度。その点について柴田氏の姿勢は明確です。「まず最初に申し上げたいのは、敵自体が弱くなったわけではなく、依然として非常に強いということです」
しかし同時に、新規プレイヤーが挫折しないための工夫と、シリーズ経験者のQoLを向上させる仕組みも随所に施されています。これは、開発チームが「プレイヤーの時間を尊重する」姿勢の表れです。
特に新規プレイヤーに対しては、ゲームの仕組みを自然と学べるよう、段階的なオンボーディング要素が導入されています。サムライスタイルでゲームを始めるとき、まず「中段の構え」から始め、その仕組みに慣れてから他の構えを学ぶことができるようになっています。これにより、プレイヤーは最初から複雑なシステムに圧倒されることなく、無理なくゲームの深みを理解していくことができます。
また、シリーズの特徴である大量のドロップアイテムについても、大幅なQoL改善が図られています。新機能の「ルートフィルター」は、特定レアリティ以下のアイテムを自動で売却・破棄する設定を可能にし、インベントリ管理の煩雑さを解消しました。さらに、プレイヤーの所持する最も強力な武器を自動で装備する機能も追加されており、ハクスラRPGとしての利便性を大きく向上させています。
戦闘システムとオンライン要素
戦闘システムでは、陰陽術の「タリスマン」が、妖怪を倒すことで入手可能になるなど、調整が施されています。また、最大3人でのオンライン協力プレイや、「血刀修羅」と呼ばれる特殊な強敵の出現など、仲間と共に楽しめる要素も引き続き用意されています。シリーズの「マスコア」な挑戦を維持しつつ、プレイヤーの時間を尊重し、熟練への道筋を丁寧に設計する姿勢は、本作の大きな魅力となるでしょう。
まとめ
柴田氏へのインタビューを通じて浮かび上がったのは、「仁王3」が単なる続編ではなく、シリーズの本質である「死闘感」と「密度」を維持した上での、大胆かつ論理的な再構築であるということでした。
「セミオープンワールド」という挑戦は、主人公の過酷な運命と時を越える物語装置と結びつき、探索に絶え間ない緊張感をもたらします。そして、二つの戦闘スタイル「サムライ」と「ニンジャ」の分離は、プレイヤーの自由度を制限するのではなく、日本の武の伝統に根ざした深遠な専門性を追求するための開発哲学の表明です。高難易度の維持とQoL改善による新規プレイヤーへの配慮は、細やかな設計によって両立されています。発売が今から待ち遠しい、期待の一作です。
情報元:wccftech