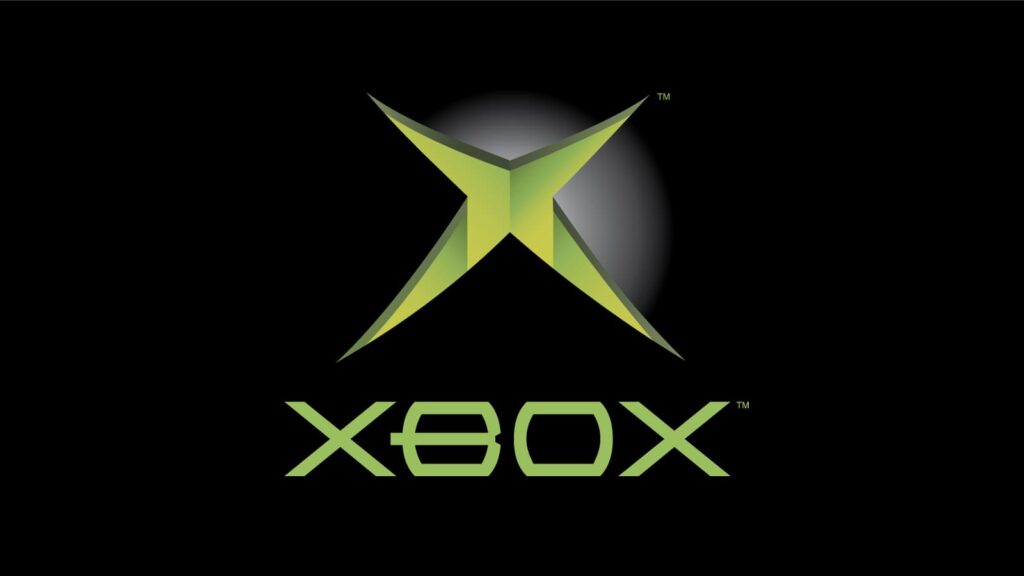
MicrosoftのXbox事業が大きな岐路に立っています。創設メンバーのローラ・フライヤー氏やBlizzard元社長のマイク・イバラ氏など、ブランドを築き上げてきた重要人物たちから、現行戦略への懸念が相次いでいます。「ハードウェアは事実上死んだ」との指摘や、パブリッシャーへの転換を促す提言は、業界に大きな波紋を広げています。
Xbox、岐路に立つブランド戦略
Microsoftのゲーム部門Xboxは、そのブランドのあり方を巡り、重大な岐路に立たされています。かつて発展を支えた元幹部や創設メンバーから現行の事業戦略に懸念や批判が相次ぎ、ゲーム業界の注目を集めています。彼らの発言は、Xboxがコンソール(家庭用ゲーム機)メーカーであり続けるのか、あるいはソフトウェアとサービス中心のパブリッシャーへ完全に舵を切るのかという、根本的な問いを突きつけているのです。
一方で、Microsoftは次世代コンソールの開発継続を明言しており、Game Passサービスも順調な成長を続けています。この複雑な状況の中で、Xboxの真の方向性を読み解くことが重要になっています。
創設メンバーが警鐘を鳴らす
この議論の火付け役は、Xbox創設メンバーの一人、ローラ・フライヤー氏です。彼女は1995年からMicrosoft Game Studiosの初期メンバーとして活動し、2000年5月にXboxプロジェクトに参加、Xbox Advanced Technology Groupのディレクターを務めました。プロデューサーとして『Crimson Skies』『Gears of War』シリーズなど数々のタイトルを手がけるなど、業界を知り尽くしたベテランです。
フライヤー氏は自身のYouTubeチャンネルで、「個人的には、Xboxハードウェアは死んだと考えています」と断言しました。その根拠として、Microsoftが最近発表したASUS製の携帯PC「ROG Ally」やMeta社のVRヘッドセットといった、外部企業とのハードウェア連携を挙げています。これらを自社開発・製造からの「緩やかな撤退」と見ており、「Xboxには意欲、あるいはハードウェアを自社で出荷する能力が失われたように見えます」と述べ、事業の終焉を示唆していると指摘しました。
また、現在のXbox戦略についても「混沌としている」と批判。「Xbox Anywhere」のスローガンを「中身のないマーケティング」と切り捨て、最終的な狙いは全ユーザーをサブスクリプションサービス「Game Pass」に誘導することにあると見ています。
さらに、「次世代のヒット作はどこにあるのか。25年後にXboxを気にかける人はいるのか」と問いかけ、過去の成功に依存する現状へ強い危機感を示します。Game Passは強力なサービスですが、そのためにハードウェアという柱を失ってよいのか、と彼女は疑問を呈しています。
Xboxはパブリッシャーに転換すべきか?
Blizzard元社長のマイク・イバラ氏も同様の懸念を示しています。同氏はかつて20年にわたりMicrosoftでXbox LiveやGame Pass事業を率いた後、3年間Blizzardの社長を務めた人物です。
イバラ氏は自身のSNSで「Xboxが何者で、どうあるべきかについて混乱しているのを見るのは辛い」と心境を吐露し、「進むべき道を一つ選び、それに専念すべきだ」と明確なビジョンを持つ必要性を訴えました。
フォロワーから具体的な提案を求められると、「Xboxは世界最大のエンターテイメントコンテンツのパブリッシャーを目指すべきだ。それ以外の全てを捨て、集中することだ」と断言。ハードウェアとソフトウェアの両方を追う現行戦略については、「中途半端な立ち位置は勝利へのプランにはならない」として、根本的な見直しを促しています。
次世代への継続的投資
これに対し、マイクロソフト側はハードウェア事業からの完全撤退を否定しています。Xbox責任者のサラ・ボンド氏は次世代コンソールの開発継続を明言しており、フィル・スペンサー氏も2026年の25周年に向けて「非常に特別な年になる」と期待を寄せています。
しかし、ボンド氏が掲げる「Windowsをゲームのナンバーワンプラットフォームにする」というビジョンは、Xboxの未来が従来の専用機とは異なる可能性を示唆します。これは、Windowsを搭載し、複数のゲームストアが利用できるPCのようなデバイスへ移行するという、フライヤー氏の指摘を裏付けるものとも解釈できるでしょう。
また、事業面ではGame Passの契約者数が堅調に推移し、最新の四半期報告でXbox部門の収益が増加していることも事実です。thumb_upthumb_down
マルチプラットフォーム戦略とデータが示す現実
元幹部たちの発言の背景には、Microsoftが進める「マルチプラットフォーム戦略」があります。かつてXboxの独占だった多くのタイトルが、今や発売とほぼ同時にライバルのPlayStation 5でもリリースされています。
この動きは、Microsoftが掲げる「いつでも、どこでも、誰とでも遊べる」というビジョンを体現する一方で、Xboxコンソールならではの優位性を損なうことにも繋がります。Xboxでしか遊べないタイトルが減れば、ハードウェアを購入する動機が弱まるためです。
市場データが示す現実
- 2024年末時点の累計販売台数:PlayStation 5が約7,100万台に対し、Xbox Series X/Sは約3,200万台
- 市場シェア:PlayStation 5が68.8%(前年比+3.0%)に対し、Xbox Series X/Sは31.2%(前年比-3.0%)
- 過去12ヶ月間でPS5はXbox Series X/Sを約1,370万台上回る販売を記録
この販売台数の大きな差は、Xboxがハードウェア戦略の見直しを迫られている現状を明確に示しています。
複数のシナリオが考えられる未来
将来的にはハードウェア事業から撤退し、クラウドゲーミング特化のサブスクリプションサービスへ完全移行する見方もありますが、現状では時期尚早と考えられます。まずは次世代ハードウェアが投入される可能性が高いでしょう。もしその次世代機が大きな成功を収めれば、Microsoftが方針を転換し、ハードウェア事業を継続する余地も生まれます。
ただ、噂されるXboxの次世代ハードウェアはPCに近いとされており、任天堂のようにハードウェアと遊びの体験を一体化させた提案には至っておらず、爆発的なヒットのハードルは依然として高いのが実情です。
一方で、Game Passの成長とマルチプラットフォーム戦略の成功により、Microsoftがソフトウェア・サービス企業として安定的な収益を確保している点も見逃せません。この成功が、元幹部たちの懸念とは裏腹に、新たなビジネスモデルとして確立される可能性もあります。
25周年という節目が、事業の方向性を明らかにする転換点となるのか、それとも現在の曖昧な戦略が続くのか。ゲーム業界全体が注目するその答えは、遠からず示されることになるでしょう。
情報元:VGC




